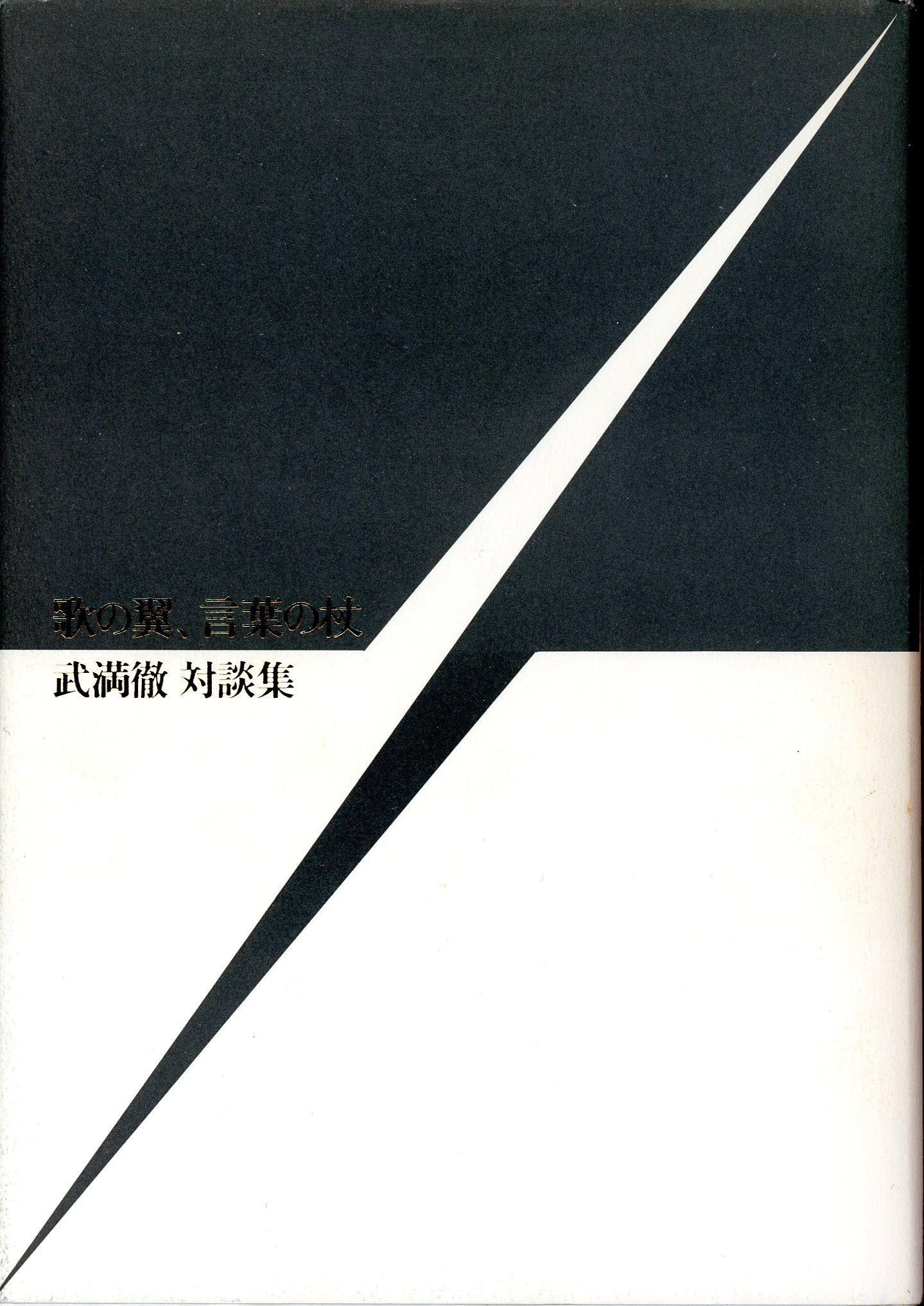
(1)武満徹対談集(歌の翼、言葉の杖)より、作曲家「尹 伊桑」との対談から(1968年)
武満 尹先生の音楽はベートーヴェン主義と論じられていることがありますね、
(に対して答えた部分)
尹 シンフォニーを書いたすぐれた作曲家はたくさんいます。チャイコフスキーとかドヴォルザークとか。
近い例ではプロコフィエフとか。しかし最もシンフォニーに作曲家の全魂を突っ込んだ人は、ベートーヴェンが代表
でしょう。
(現代音楽が前衛に行きすぎている反動として・・・)
武満 耳がかわってきたということで言えば、最近僕はベートーヴェンなんかを聴いて、本当に面白いと思うんです(笑)
尹 やはり我々の聴き方が本当に変わってきたでしょうね。昔は、耳に邪魔されて、チャイコフスキーなんかはほとんど
聴けなかった。 ドヴォルザークも、今はとても美しいじゃないですか・・・。
(2)雑誌「ポリフォーン」1991年8月号武満徹総特集(武満徹の連載対談「指揮者サイモン・ラトル」より
サイモン・ラトルとの対談「オーケストラに未来はあるか」で語っていたこと。。
今から30年前の雑誌なのでオーケストラの未来への考え方などは当時からすれば少し修正が必要かもしれません。
今、この問題を取り上げることではなく、この記事の中で武満徹が語っていたひとことが武満徹らしいなと思って再現してみた。
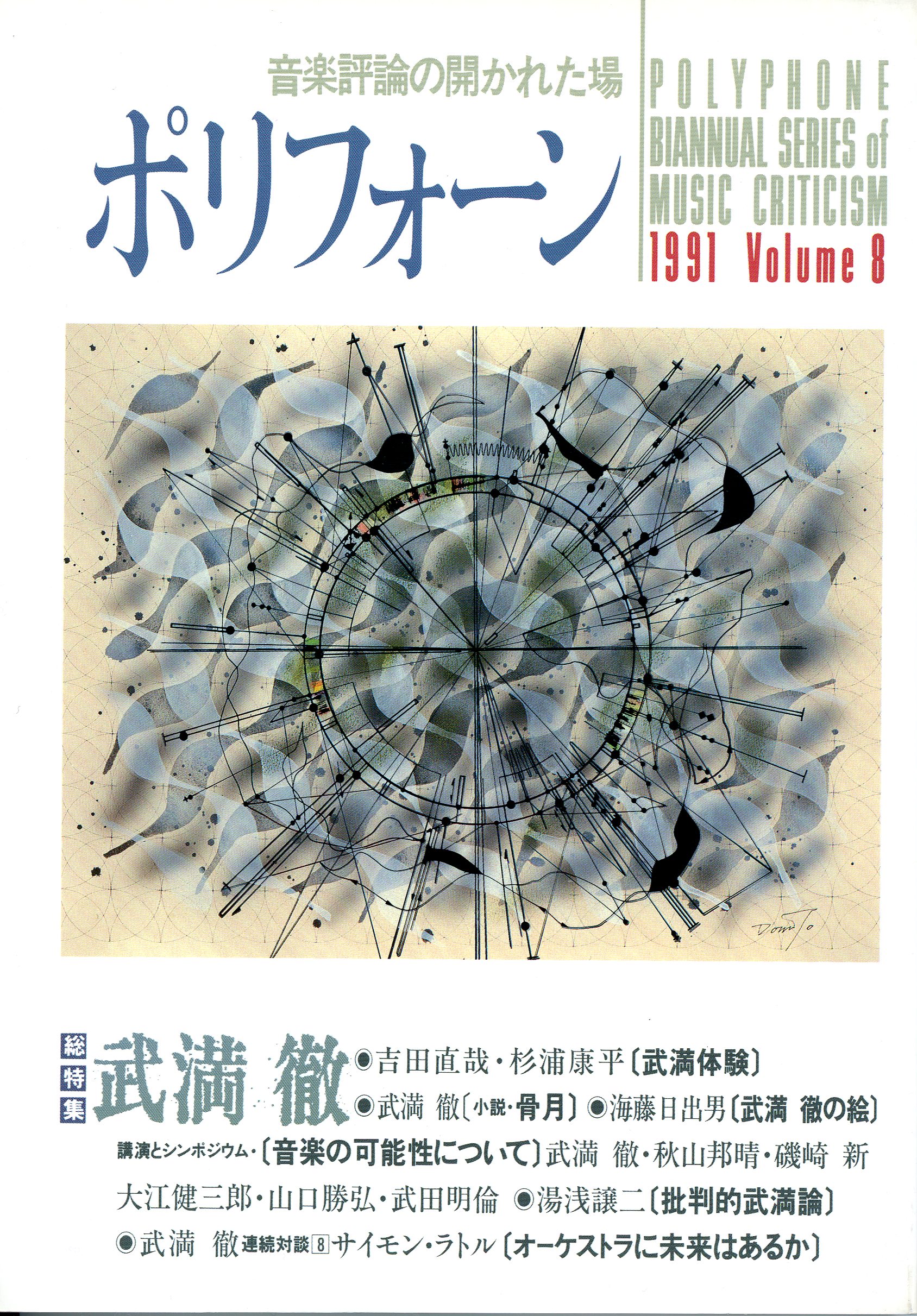
ラトルが、”現代の演奏は陳腐化した型通りの演奏の再生産しか望みえない”と危惧していることに対し、
武満も同様な危惧を感じていると言い、 “例えばドヴォルザークに「新世界より」という名曲がありますが、この曲なんかが良い例で、今ではあまりに手垢がついてしまい、演奏の表情をつけるルバートがすべてルーティンになってしまっていて、
ただ甘ったるいだけの、まるっきり楽譜を無視したような演奏が最上のものとして流通しているわけです。
ところが以前に岩城宏之さんがあの楽譜をきちんと読んで、指示通りに、つまりあの曲が持っている古典的な性格に忠実に演奏した僕の耳には実に新鮮に聞こえた・・・” と語っていた。
ここで、私が注目したいのは、武満徹が、「新世界より」が今は手垢がついた演奏になっているということと、
岩城宏之が演奏した「新世界より」は新鮮だった、と述べておられるということは上述のように、この曲を名曲と言っており、
結構聴いて来ていたことが分かります。
ただこれだけのことですが、ドヴォルザークのファン(クラシック音楽界では似つかわしくない言葉かもしれませんが)としては
尊敬する武満徹がドヴォルザークも聴いていたというだけで満足です。
ついでに、サイモン・ラトルとドヴォルザークの関係についても述べたいけれども、作曲家ではないので別項で扱います。
更についですが、この雑誌「ポリフォーン」では、武満徹が連続対談として連載しており、8回目にサイモン・ラトルが選ばれ
ましたが、ラトルとバーミンガム・シンフォニーの演奏会でメシアンの「トゥーランガリラ」を聴いて武満徹が深い感動を受けた
ことが発端のようです。
(3)池辺晋一郎「ドヴォルザークの音符たち~新ドヴォルザーク考」の著書より
(楽譜に並んだ音符たちから見えてくるものを、作曲家の立場に立って論じるといったユニークな内容のシリーズ本)
このシリーズは、「バッハの音符たち」から始まり、モーツァルト、ブラームス、シューベルト、ベートーヴェン、シューマンといったドイツ系大作曲家の刊行が済ん
で、次はロマン派の出番ということになるが、その最初に、ドヴォルザークが選ばれた。
池辺氏は、私が尊敬している現代を代表する作曲家です。ドヴォルザークが大好きを憚らず、早く「ドヴォルザークの音符たち」を書きたいといった意中が、
最初の頁から伝わってくる。この本は、第1章から第24章までの、全21曲を解説したもので、その中で好きだという「ピアノ協奏曲」や「交響曲第3番」、「チ
ェロ協奏曲(イ長調の習作の方)」など、マイナーな曲も取り上げられている。内容は改めて別の項で述べたい。
次の2行が全てを語っている(本文より)。
●美しいメロディを次々に“出し過ぎる”傾向のあるドヴォルザーク。
メロディの山!メロディの連鎖!これがドヴォルザークなのだ!
●ドヴォルザークは「近代の足音」とともに生きた人だった。
その音符たちには、近代と民族の、魂の響きが、五線からはみ出すほどに詰まっている。
次に、過去にエアチェックしたNHK-FM放送の番組「N響定期公演」からの2件を再現
(4)第1718回N響定期公演から、野平一郎(ゲスト)、山田美也子(アナ)
ラドミル・エリシュカ指揮NHK交響楽団で、ドヴォルザークの交響曲第6番の演奏ライブ(NHKホールから中継)2012年4月16日
野平一郎氏は、現代作曲家ですがピアニストとして、こちらの方が有名かな。
今回の演奏について、実際に客席で聴いて来たのちスタジオに戻ってから感想を述べられたが、開口一番「いやー、凄い演奏でした。構築力の素晴らしさ、聴衆の反応も
すばらしいです。」とご満悦。
「この交響曲はフルメニューと言ってよいもので、最後まで引っ張られ流れてゆき、そうそうには無い演奏だと思った。」「最後の方で、音が重なり合ってくるところは
ドキドキしました(これは、女性アナウンサーの言葉で、野平氏もうなずいていた)」
「演奏を聴く前は、ブラームスの交響曲第2番を意識して作曲したと言われており、ちょっと重たい曲かなと思っていたが、全くそんなことはなく、ドヴォルザークの
田園交響曲といってもよく、木管楽器の鳥のさえずりなど、とても魅力的な曲です。」と、感動された様子を目に見える如くに話されていた。野平さんが客席から戻り、こ
の話をされているあいだ中も聴衆の興奮と歓声が続いており、この交響曲と演奏がいかに素晴らしいものだったかを物語っていた。
(5)第1792回N響定期公演から、西村朗(解説)、山田美也子(アナ)
下野竜也指揮NHK交響楽団で、ドヴォルザークの交響曲第6番の演奏のライブ (サントリーホール)2014年11月9日
西村朗さんは、日本を代表する現代作曲家ですが、古典、ロマン派の音楽、作曲家の歴史にも詳しく、演奏の始まる前は、アナウンサーの質問などに答えて、ドヴォル
ザークの交響曲第6番の作曲へ至るまでのブラームスとの関わりなどを分かりやすく解説していた。
演奏中は、西村氏がスタジオを出て、実際に客席へ行って演奏を聴き、終わった後に戻って来てもらい感想を述べてもらった(聞き取りのため、若干ニュアンスの相違は
あります)。
山田アナ 「演奏どうでしたか。」
西村氏 興奮気味に「良かったですねー。うーん、この曲の歴史的名演ではないでしょうか」
「本日、ここにくる前に、この交響曲第6番の過去の演奏をいくつか聴いてきましたが、本日の演奏はすごいテンションで圧倒されました。」
山田アナ 「下野さんは生き生きと指揮をされていましたね」
西村氏 「いやー、下野さんはこの曲が好きなんですね。この曲の魅力を伝えたいという使命感をもって最高の演奏をされたのではないでしょうか。N響もよく答えて
いました。」
山田アナ 「まだ、熱狂が止まず、下野さんがまた指揮台に立たれ、観衆の声援にこたえています。これは曲が素晴らしいのですといった仕草をしております。」
西村氏 「この曲は、若いドヴォルザークの力量が発揮されていて、下野さんの輝かしい指揮にN響がオーラを受けて素晴らしい演奏になったと思います。」
「僕は、ドヴォルザークの前に立たされたら?泣いてしまうかもしれない。」
「ドヴォルザークは、後年、ヨーロッパを席巻し、さらにアメリカまで名を轟かせた人です。」
「下野さんは、こういった隠れた名曲を、4番などもやってもらいたいですね。」
西村氏は、解説中に演奏について「本当にびっくりした」と何度も言っておられた。
西村朗氏は複雑な楽譜を表し、難解な「現代音楽」のすごい作曲家ですが、以上のように素直に反応してくれて決してドヴォルザークをメロディだけの人とは言いません。
また、事前にこの曲の過去の演奏を聴いてきた(予習)など、その真摯な態度は、お人柄の良さが滲み出ております。
今回2件の紙上再現は、偶然にもドヴォルザークの交響曲第6番といった一般的にはマイナーな曲の競演になったが、私が好きな曲だけあって、音源が残っていたのが
幸いだった。
(追記)
この記事を書きながらNHK大河ドラマ(晴天を衝け)を観ていた(5月2日)が、書き終わったので、他のTV番組表を何気なく見てみると、偶然というか驚いたことに
10時から、NHK教育番組「クラシック音楽館」で「熊倉優」指揮NHK交響楽団による「ドヴォルザークの交響曲第6番」が演奏されるとあった。
この偶然については置いておき、数年ぶりにこの曲を聴いて、改めて曲の素晴らしさを再認識させられた。
指揮者の「熊倉優」は若手の俊英で、3年前からN響と関わりを持ち、今、もっとも期待されている新人とのこと。残念なのは、なぜこの交響曲第6番を演奏することにしたのか説明がなかった。しかし、第3楽章の民族舞曲のリズムをN響のベテラン奏者の助言にインスパイアされ、自分なりに工夫してみた。とのことで、この曲に懸ける意気込みを感じた。演奏の内容は、うっとりと聴いていたことでよく分からなかったが、良かったということでしょう。
(追記の蛇足)
何か、追記の記述が多くなってしまった。眠くなったがテレビを観終わり、書いた内容にもう一度目を通すと(普通は行わないが、偶然がもたらした反動か)、いつものことながら紋切り型文章の表現が目立つがどうしょうもない。
また、「見てみる」や「置いておく」といった同じ文字の連なりがあり、文章として間違っていないか?とネットで調べてみた。経緯が長くなるので割愛するが、結果は間違いではないと分かった(いまさら、なぜに)。結局、校正をせずにそのままで終わった。
(つづく)不定期